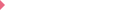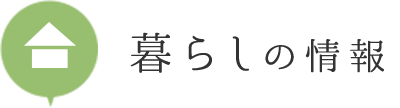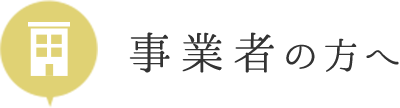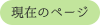後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について
原則75歳以上(一定の障害がある方で広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満)の方が加入し、都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が市町村と連携・協力して運営します。
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
- 65歳以上75歳未満の方で、広域連合により一定の障害があると認められた方
障害認定の手続きには、国民年金証書または身体障害者手帳等と現在お持ちの健康保険証をお持ちのうえ、住民課に申請してください。
後期高齢者医療制度の保険料
保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
保険料の決まり方
1年間保険料=均等割額+所得割額
※1 保険料の賦課限度額は80万円です。
保険料率
保険料率は、2年ごとに見直され、和歌山県内では均一となります。
令和6・7年度の保険料率
・均等割額 54,428円(年額)
・所得割率 11.04パーセント
保険料に係る軽減について
1. 均等割額にかかる軽減
世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
軽減基準(令和7年度)
| 軽減割合 | 均等割額 |
世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の 合計が下記に該当する世帯 |
| 7割 | 16,328円 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
| 5割 | 27,214円 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) +被保険者数×30.5万円以下 |
| 2割 | 43,542円 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) +被保険者数×56万円以下 |
65歳以上の公的年金受給者の方は、年金に係る所得から15万円を控除して軽減判定されます。 総所得金額等には、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。 年金・給与所得者とは、以下のいずれかを満たす方です。 ※給与専従者収入額減算後の給与収入が55万円を超える ※前年の12月31日現在65歳未満の方で公的年金等収入額が60万円を超える ※前年の12月31日現在65歳以上の方で公的年金等収入額が125万円を超える
2. 被用者保険の被扶養者にかかる軽減
被用者保険の被扶養者であった方
制度加入の前日に被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割がかからず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減されます。
保険料の納付の方法
保険料の納め方は、年金の受給額によって、年金からの天引き(特別徴収)と納付書や口座振替による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。
1.公的年金からの天引き(特別徴収)
2カ月に1回支給される年金からの天引きによって納めていただきます。特別徴収の対象となる方は次のとおりです。
・公的年金などの支給額が年額18万円以上の方
・介護保険料と合わせた保険料額が年金の2分の1を超えない方
特別徴収の対象となる年金が二つ以上受給している場合は、別紙に掲げる順序に従い、一つの年金を選択して特別徴収が実施されます。この年金は、介護保険料が引かれている年金と同じものになります。
2.納付書や口座振替による納付(普通徴収)
上富田町から送付される納付書または口座振替で保険料を納めていただきます。 特別徴収の対象とならない方は、次のとおりです。
・年金が年額18万円未満の方
・介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の2分の1を超える方
・年度途中で75歳になった方
・年度途中で他の市町村から転入した方
【注】納期限までに完納されなかった場合は、督促状の発行や滞納処分を受けなければならないことがあるほか、条例の定めにより督促手数料や延滞金が徴収されます。滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告が行われます。さらに、滞納処分の対象となり、財産調査により、年金、預貯金、給与、不動産等の財産が差し押さえられることがあります。
口座振替について
納付書または年金からの天引きの方は、口座振替に変更することができます。希望される方は、上富田町の指定金融機関にて手続きを行ってください。また、年金からの天引き(特別徴収)の方につきましては、役場でも手続きが必要ですので、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)持参し、住民課で手続きをお願いします。
後期高齢者医療制度の給付
医療費は、かかった費用の1割(所得により2割または3割)を一部負担金として自己負担します。一部負担金の割合は、前年の所得状況により、毎年判定をします。
病院等の窓口で払う自己負担額(一部負担金)の割合
令和4年10月から
| 所得区分 | 負担割合 | |
| 現役並み所得者 | 3割 |
1.住民税の課税標準額が145万円以上の被保険者 ただし、次の場合は申請することにより1割または2割負担となります。 |
| 一般II | 2割 | 住民税の課税標準額が28万円以上で、かつ、「年金収入とその他合計所得金額」の合計額が200万円(世帯に被保険者が二人以上いる場合は320万円)以上の方 |
| 一般I | 1割 | 現役並み所得者、一般II、低所得者II、低所得者I以外の方 |
| 低所得者II | 1割 | 世帯の全員が住民税非課税の方 |
| 低所得者I | 1割 | 世帯の全員が住民税非課税の方で、各種収入等から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金の所得は控除額を80万円として計算) |
限度額適用・標準負担額減額認定について
低所得者II、低所得者Iに該当する方及び現役並所得者で課税所得690万円未満の方は、住民課で申請することにより負担割合と限度額区分が併記された資格確認書が交付されます。医療機関窓口へ提示することにより、窓口での支払いが自己負担の上限額までの支払いとなります。
申請する際に必要な書類等
- 資格確認書
- 窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
高額療養費
同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | |||
|
現役並み所得者 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント [140,100円] |
||||
|
現役並み所得者 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント [93,000円] |
||||
|
現役並み所得者 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント [44,400円] |
||||
| 一般I・II |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 [44,400円] |
|||
| 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |||
| 低所得者I | 8,000円 | 15,000円 | |||
現役並み所得者及び一般で、過去12ヶ月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合は、 4回目以降の外来+入院の限度額が[ ]内の金額となります。
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の両方で、毎年8月から翌年7月の一年間に支払った自己負担額(高額療養費または高額介護サービス費として支給した金額を除く)を合算して自己負担限度額(下表)を超えた部分をそれぞれ按分し支給します。
| 後期高齢者医療+介護保険 | |
| 現役並み所得者(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 現役並み所得者(課税所得380万円以上) | 141万円 |
| 現役並み所得者(課税所得145万円以上) | 67万円 |
| 一般I・II | 56万円 |
| 低所得者II | 31万円 |
| 低所得者I | 19万円 |
入院時食事療養標準負担額(1食あたり)
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
| 所得区分 | 1食当たり |
| 現役並み所得者、一般I・II | 510円(注1) |
| 低所得者II(区分II)90日までの入院 | 240円 |
| 低所得者II(区分II)過去12か月で90日を超える入院 | 190円(注2) |
| 低所得者I(区分I) | 110円 |
(注1)指定難病の方については、300円。平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病棟に入院していた方で、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は、260円。
(注2)適用には申請が必要です。
入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
| 所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
| 現役並み所得者、一般I・II | 510円(注1) | 370円 |
| 低所得者II(区分II) | 240円 | 370円 |
| 低所得者I(区分I) | 140円 | 370円 |
| 老齢福祉年金受給者境界層該当者 | 110円 | 0円 |
入院医療の必要性の高い方(人口呼吸器、静脈栄養等が必要な方)、指定難病の方
| 所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
| 現役並み所得者、一般I・II |
510円(注1) 指定難病の方は300円 |
370円 指定難病の方は0円 |
|
低所得者II(区分II) 90日までの入院 |
240円 |
370円 指定難病の方は0円 |
|
低所得者II(区分II) 90日超える入院 |
190円(注2) |
370円 指定難病の方は0円 |
| 低所得者I(区分I) | 110円 |
370円 指定難病の方は0円 |
| 老齢福祉年金受給者境界層該当者 | 110円 | 0円 |
(注1)医療機関の施設基準等により、470円の場合もあります。
(注2)適用には申請が必要です。
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。療養を受けられた方は、住民課で払い戻しの手続きをしてください。
- やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具をつくったとき
- 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき
(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます) - 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
- 輸血のために用いた生血代がかかったとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき
訪問看護療養費
居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用の1割、所得により2割または3割)を支払い、残りを後期高齢者医療が負担します。
移送費
負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。救急車は無料なので対象になりません。
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部など)の場合、同一月に同一医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担限度額は月額1万円です。特定疾病療養受療証が必要になりますので、住民課に申請してください。
生活習慣病の早期発見のため、検診を受けましょう
75歳以上の方についても、糖尿病や高血圧性疾患などの生活習慣病を早期発見・治療していただくために、下記の検査を実施します。
健康診査について
健康診査・歯科健康診査の対象の方には、5月下旬に和歌山県後期高齢者医療広域連合より受診券を送付します(受診券発行の申込の必要はございません)。
人間ドックについて
一日ドック、脳ドック
白浜はまゆう病院、紀南病院、玉置病院、南和歌山医療センター
一日ドック
まちだ内科クリニック、竹村医院
受検までの流れ
- 住民課の窓口で人間ドック受検予定日で申し込みを行って下さい。
- 後期高齢者医療担当から、ご本人宛に人間ドック助成券を送付します。
- 助成券が届いたら直接ご本人が病院に受検日を予約していただきます。
(助成券の有効期限内で予約願います。) - 予約日に人間ドック助成券と自己負担金を持参して、検査を受けて下さい。
申し込みは、被保険者証、来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)をお持ちの上、住民課までお越し下さい。
後期高齢者医療制度の詳しい内容について
和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民課 保険班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005
更新日:2025年10月01日